あなたの作品が、知らぬ間にAIの”教材”になっていたとしたら?
夕暮れのカフェで、友人のイラストレーターがスマートフォンをじっと見つめながら、ぽつりとつぶやきました。
「これ…私の絵にすごく似てる。でも、描いた覚えがないんだよね」
画面に映っていたのは、生成AIがつくり出した1枚のイラスト。
色づかいや構図、細かいタッチまで、彼女が過去に投稿した作品にそっくりでした。
「まさか、私の絵がAIに”学ばれて”いたのかな…」
その言葉は、まるで独り言のようでしたが、私の胸に刺さりました。
もしかしたら、自分の作品も、誰かの詩も、写真も、知らないうちにAIの”材料”として使われているのではないか──そんな不安を、私たちは今、共有し始めています。
「技術のために、少しぐらい我慢して」──誰のためのバランス?
この問題に大きな注目が集まるきっかけとなったのが、2024年3月に発表されたトニー・ブレア研究所(TBI)の報告書「Rebooting Copyright: How the UK Can Be a Global Leader in the Arts and AI(著作権の再起動:英国がいかにしてアートとAIのグローバルリーダーになれるか)」でした。
この報告書は、AIと著作権の未来について提言をまとめたもの。
その中で繰り返し語られているのは「著作物の利用には柔軟性を持たせるべきだ」という考え方です。
つまり、AIが学習のために著作物を利用することを、全面的に規制してしまうのは現実的ではない。
イノベーションを止めないためにも、ある程度の自由な使用は許容されるべきだ──という立場が取られていました。
報告書は特に、権利者が「オプトアウト(参加拒否)」できる仕組みを提案しています。
しかし、この提言に対し、多くのクリエイターや著作権団体が強い懸念を表明しました。
Fairly Trained 社の CEO、Ed Newton-Rex は、オプトアウト方式は実際には権利者の管理を減少させると批判し、また機械学習を人間の学習と同等視する報告書の姿勢にも疑問を呈しています。
さらに、小説家の Jonathan Coe は、報告書の5人の共著者が全て科学技術分野の出身で、アーティストや創作者が1人も含まれていないことを指摘しました。
なぜなら、その「柔軟性」という言葉が、彼らにとっては「黙認」や「放任」に聞こえてしまったからです。
作品は、データなんかじゃない。人生そのものだ。
思い出してみてください。
あなたが初めて詩を書いたときのこと。
誰にも見せたことのない落書きに、少しだけ心が躍った日のこと。夜通し曲をつくったあの静かな部屋の時間のこと。
創作とは、ただ何かを「作る」ことではありません。
そこには、その人の感情があり、記憶があり、ときには傷や希望すら込められています。
AIが使う「学習データ」としての作品は、そうした個人の想いをまるごと”食材”にしているのです。
たとえるなら、それは誰かの心の種を、断りなく摘み取っていくような行為に近いのかもしれません。
それを正当化するような声が、公的な機関から発せられることに、多くのクリエイターがショックを受けたのは当然のことだったでしょう。
AIを敵にするんじゃない。ただ、置き去りにされたくないだけ。
もちろん、AIそのものが悪者だと言いたいわけではありません。
AIはすでに、医療の診断精度を高めたり、気候変動の予測に活用されたりと、人間の暮らしを豊かにしてくれる存在になっています。
TBI の報告書も、AIは人間の創造性の終わりではなく「新しい形のオリジナリティへの道を開く」と主張しています。
でも、問題はその進化のスピードではなく、進化の”あり方”です。
AIが便利になる一方で、創る人の権利や感情が後回しにされているように感じる。
そうした「誰にも拾われない小さな声」が、今回の報告書をきっかけに噴き出したのです。
「技術革新のためだから、ちょっと我慢して」──その言葉に、どこか置いてきぼりにされたような気がする人が、今、増えているのかもしれません。
もしこのままなら、創ることをやめる人が出てくる
誰かの創作が、無断で学習され、それを真似た作品が大量に出回る。
それを「仕方ない」とする世の中になってしまったら、どうなるでしょうか。
「どうせまたAIに使われるし」と、発表をあきらめる人が出てくる。
「もう描かなくても、AIがやってくれるし」と、筆を折る若者が出てくる。
それは本当に、私たちが望む未来でしょうか?
テクノロジーが進化することは素晴らしい。
けれどその進化の過程で、人間が「創ること」に対する情熱を失ってしまうとしたら、それはとても静かな喪失です。
技術を選ぶ前に、私たちは”人としての選択”をする
AIがどう進化するかは重要ですが、それ以上に大切なのは「私たちがそれをどう使うか」という意思です。
どこまでを許し、どこからを守るのか。
何を大切にし、どんな未来を描くのか。
それを決めるのは、テクノロジーではありません。
私たち一人ひとりの想像力と選択です。
トニー・ブレア研究所の報告書は、政策的な提案以上に「今、社会はどこへ向かおうとしているのか」という問いを私たちに突きつけているようにも感じられます。
英国政府は Keir Starmer 首相が2025年1月13日に発表した「AI機会行動計画」を通じて、AIのグローバルリーダーになる野心を表明していますが、技術の進歩と創作者の権利のバランスをどう取るかは依然として大きな課題です。
最後に──それでも、描く人がいる限り
AIがどれだけ賢くなっても、そこに「想い」は宿りません。
誰かの心が震えて描いた絵。
何度も書き直してようやく完成した詩。
そんな作品には、AIでは真似できない”温度”があるのです。
私たちがその温度を守りたいと願う限り、この社会はまだ、人間の手で形づくられていけるのだと思います。
どうかあなたの光を、あきらめないでください。
その光こそが、AI時代における「希望」なのですから。
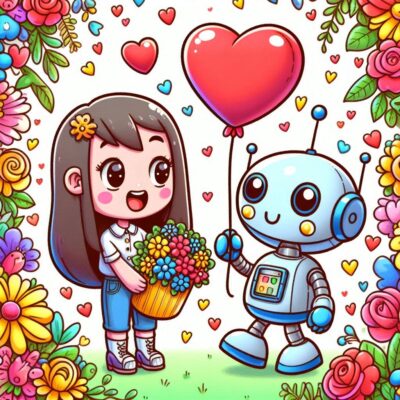
コメント