近年、人工知能(AI)技術の進化は加速度的に進み、中国市場でも数々のAIスタートアップが誕生している。
そんな中、新興企業「Manus」の登場が注目を集めている。
「第二のDeepSeek」との声も聞かれるが、果たしてその実態はどうなのか。
本記事では、Manus の特徴や DeepSeek との違い、そして中国のAI業界における位置付けを詳しく分析する。
Manus とは何者か? その技術と戦略
Manus は中国企業「The Butterfly Effect」が開発した「agentic(エージェント型)」AIプラットフォームで、先週プレビュー版が公開されたばかりだ。
Manus は完全に独自開発されたものではなく、Anthropic の Claude やアリババの Qwen など既存のAIモデルを組み合わせて微調整したものを使用している。
研究レポートの作成や財務書類の分析などのタスクを実行するために、これらのモデルを活用しているとされる。
Hugging Face のプロダクト責任者は Manus を「これまで試した中で最も印象的なAIツール」と評し、AIポリシー研究者の Dean Ball は「最も洗練されたAIを使用したコンピュータ」と称している。
Manus の Discord サーバーは数日で 13万8000人以上のメンバーを集め、招待コードは中国の転売アプリ Xianyu で数千ドルで取引されているという報告もある。
DeepSeek との違い——3つの視点で比較
Manus が「第二のDeepSeek」になれるのかを考える上で、以下の3つの視点から比較してみよう。
- 技術的なアプローチ
DeepSeek は自社開発のAIモデルを構築しているのに対し、Manus は既存モデルを組み合わせて微調整している。
この根本的な違いは、両社の技術的な独自性や長期的な競争力に大きな影響を与える。
DeepSeek は多くの技術をオープンに公開しているが、Manus はまだそうしていない。 - 実際の能力と性能
多くの初期ユーザーによると、Manus はその宣伝ほどの万能薬ではないようだ。
AIスタートアップ Pleias の共同創業者 Alexander Doria は、Manus をテスト中にエラーメッセージや無限ループに遭遇したと報告している。
他のユーザーは、事実に関する質問で間違いを犯し、情報の引用も一貫して行われておらず、オンラインで簡単に見つかる情報も見逃すことがあると指摘している。 - マーケティングと市場での位置づけ
中国メディアは Manus をAIの画期的な進歩として宣伝することが早かった。
QQ News は「国産品の誇り」と呼び、ソーシャルメディア上のAIインフルエンサーたちは Manus
の能力に関する誤った情報を広めていた。
広く共有された動画では、複数のスマートフォンアプリで操作を行うデスクトッププログラムが表示されていたが、Manus の研究リーダーである Yichao “Peak” Ji 氏は、この動画が実際には Manus のデモではないことを確認している。
Manus の現状と課題
実際のところ、Manus の実用性は限定的である。
例えば「配達範囲内の高評価のファストフード店からフライドチキンサンドイッチを注文する」という比較的単純な要求に対して、Manus は約10分後にクラッシュした。
2回目の試行では条件に合うメニュー項目を見つけたものの、注文プロセスを完了することはできなかった。
同様に、NYC から日本への航空便予約を依頼した際も、明確な指示(「ビジネスクラスの航空便を探し、価格と柔軟な日程を優先する」)を与えたにもかかわらず、Manus ができたのは複数の航空会社のウェブサイトや Kayak などの航空運賃検索エンジンへのリンクを提供するだけだった。
徒歩圏内のレストランのテーブル予約やナルト風の格闘ゲームの構築など、他のタスクでも同様に失敗している。
Manus の広報担当者は「小さなチームとして、私たちの焦点は Manus を改善し続け、ユーザーが問題を解決するのを実際に支援するAIエージェントを作ることです。現在のクローズドベータの主な目的は、システムのさまざまな部分をストレステストし、問題を特定することです」と述べている。
結論——Manus は「第二の DeepSeek」ではない
現在のところ、Manus を DeepSeek と同じ路線で語るのは誤りだ。
The Butterfly Effect 社は DeepSeek とは異なり、社内モデルを開発しておらず、技術的アプローチも大きく異なる。
Manus の急速な人気は、技術的革新よりも、招待コードの希少性や中国メディアによる国産品としての誇張、ソーシャルメディア上での誤った情報拡散によるところが大きい。
Manus はまだ非常に初期のアクセス段階にあり、The Butterfly Effect 社はコンピューティング能力の拡張や報告される問題の修正に取り組んでいると主張している。
しかし現状では、Manus は技術的革新よりも誇大宣伝が先行している事例のように見える。
中国のAI市場は今後も急速に成長し続けるだろう。
その中で、Manus が真に革新的なプラットフォームへと進化するのか、それとも一時的な話題に終わるのか、今後の展開に注目していきたい。
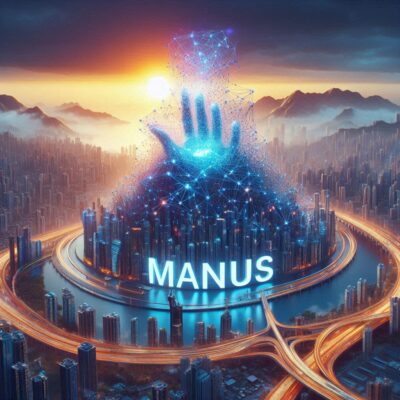
コメント