「えっ、これって偽物なの?」──信じられないほどリアルなAI画像
ある日、スマホの画面に表示された1枚のレシート画像。
いつも使っているスーパーのロゴ、見覚えのある商品名、日付、金額、フォントの太さまで、まるで実際に買い物をした直後に渡されたもののように見える。
ところが、それが実はAIによって作られた”偽物”だったとしたら、あなたはすぐに気づけるでしょうか?
いま、そんな「信じられないほどリアルなニセモノ」をAIが簡単に作れてしまう時代がやってきています。
特に 2025年3月に登場した、OpenAI の ChatGPT に新しく加わった GPT-4o モデルの画像生成機能が、世界中で大きな話題を呼んでいるのです。
ChatGPT がレシート画像を作る時代──言葉からリアルを生み出す力
ChatGPT と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは文章を作るAIかもしれません。
質問に答えてくれたり、メール文を書いてくれたり、作文を手伝ってくれたり。
けれども今回の進化は、そのさらに先を行くものでした。
OpenAI が新たに統合した画像生成機能は、ChatGPT の GPT-4o モデルの一部として動作する最新のツールです。
この機能は特に画像内のテキスト生成が大幅に向上しています。
使い方はいたってシンプル。
「レストランのレシートのような画像を作って」と指示するだけで、数秒後にはまるで本当にその場で発行されたような画像が目の前に現れます。
すでに SNS では様々な実例が共有されています。
有名なVC(ベンチャーキャピタリスト)の Deedy Das 氏はXに、サンフランシスコの実在するステーキハウスの偽のレシート画像を投稿。
他にもフランスの LinkedIn ユーザーは地元のレストランチェーンの、しわくちゃになったレシート画像を生成し、さらに TechCrunch はサンフランシスコの Applebee’s の偽レシートの生成に成功しています。
さらには食べ物や飲み物のシミがついた、より本物らしく見えるレシート画像を作成した例も報告されています。
「リアルすぎる偽物」が引き起こす、現実的なリスク
しかしながら、こうした進化には裏の顔もあります。
便利で魅力的な技術である一方、その”本物らしさ”が悪用される可能性が高まっているのです。
AIで生成されたレシート画像にも、まだいくつかの「偽物である証拠」が残っています。
TechCrunch が生成した Applebee’s のレシートでは、合計金額にピリオドではなくカンマが使われていたり、計算が合わなかったりといった明らかな不自然さがありました。
LLM(大規模言語モデル)は基本的な計算でもまだ苦戦しているため、これは特に驚くことではありません。
しかし、詐欺師が画像編集ソフトウェアでこれらの数字をすぐに修正するか、あるいはより精密なプロンプトで生成することは難しくないでしょう。
たとえば、会社の経費申請で存在しない出張費をでっち上げたり、実際には購入していない商品の返金を求めたりするために使われる可能性があります。
これらのケースでは、画像をひと目見ただけではなかなか偽物と判断できないため、見破るのが非常に困難です。
こうしたリスクについて、OpenAI の広報担当者 Taya Christianson 氏は TechCrunch に対し、ChatGPT で作成されたすべての画像にはAIによって作成されたことを示すメタデータが含まれると説明。
さらに同氏は、OpenAI は利用ポリシーに違反するユーザーに対して「措置を講じる」とし、実際の使用状況やフィードバックから「常に学んでいる」と付け加えました。
TechCrunch がなぜ ChatGPT が最初から偽のレシートの生成を許可しているのか、またこれが OpenAI の利用ポリシー(詐欺行為を禁止している)に沿っているのかを尋ねたところ、Christianson 氏は、OpenAI の「目標はユーザーに可能な限り創造的な自由を与えること」であり、AI生成の偽レシートは「金融リテラシーを教える」といった詐欺以外の状況や、オリジナルのアートや商品広告の作成にも使用できると回答しました。
本物と偽物の境界が、少しずつ曖昧になっていく
「写真は真実を写すもの」
かつて、そう信じられていた時代がありました。
でも今は違います。
画像も、文章も、音声さえも、AIの力によって”もっともらしい形”で自由自在に生み出せる時代です。
もはや「見たから信じる」という判断だけでは十分ではありません。
「誰が、何のために、どんな技術を使って作ったのか?」という背景までを考える習慣が、私たちの日常に必要になってきたのです。
特に今回のように、何気ない一枚のレシート画像が持つ”信頼の力”をAIが完全に再現できてしまうとなると「本物らしさ」が揺らぐだけでなく「本物の意味」そのものが変わり始めているようにも感じられます。
恐れるのではなく、付き合い方を学ぶという選択肢
もちろん、こうした技術の進歩に対して「怖い」「危ない」と感じるのは自然なことです。
でも、AIが進化することそのものを否定する必要はありません。
大切なのは、それをどう使い、どう受け止めるか。
つまり”付き合い方”の問題なのです。
例えば、映画やテレビドラマの小道具として、リアルなレシート画像を簡単に作れるようになったことで、制作現場の効率は格段に上がるでしょう。
教育の現場でも、偽と本物を見分けるための教材として活用できるかもしれません。
OpenAI が主張するように、金融リテラシーを教えるための道具としても役立つかもしれません。
発想次第で、この技術は大きな可能性を秘めているのです。
包丁が料理にも凶器にもなるように、AIもまた創造の道具にも、誤用のリスクにもなります。
だからこそ、AIと共に生きる私たちは「技術に流される」のではなく「技術と向き合う」姿勢が求められているのです。
レシート一枚から見えてくる、「信頼」のこれから
最後に、もう一度考えてみてください。
あなたが普段何気なく目にしているもの──レシート、写真、ニュース記事。
どれも”本物”に見えるから信じている、という側面はないでしょうか?
でもこれからは、目に見えるものだけを頼りに判断するのではなく、その背後にある”意図”や”仕組み”まで想像する力が求められます。
そして何より、私たち自身が「これは本当に信じていい情報なのか?」と自らに問いかける習慣を持つことが、今後の社会において何よりも大切になってくるのです。
レシート一枚から広がったこの話は、単なるテクノロジーの話題ではありません。
これは「信頼」や「現実」とは何かを私たちに問い直す、ひとつの大きなきっかけなのです。
参考:ChatGPT’s new image generator is really good at faking receipts
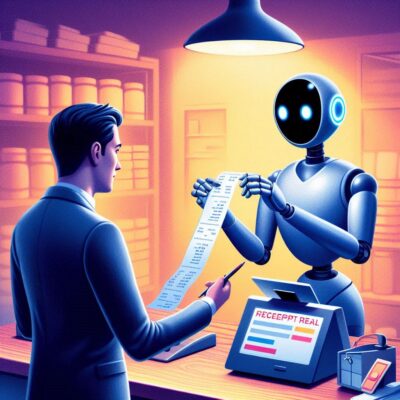
コメント